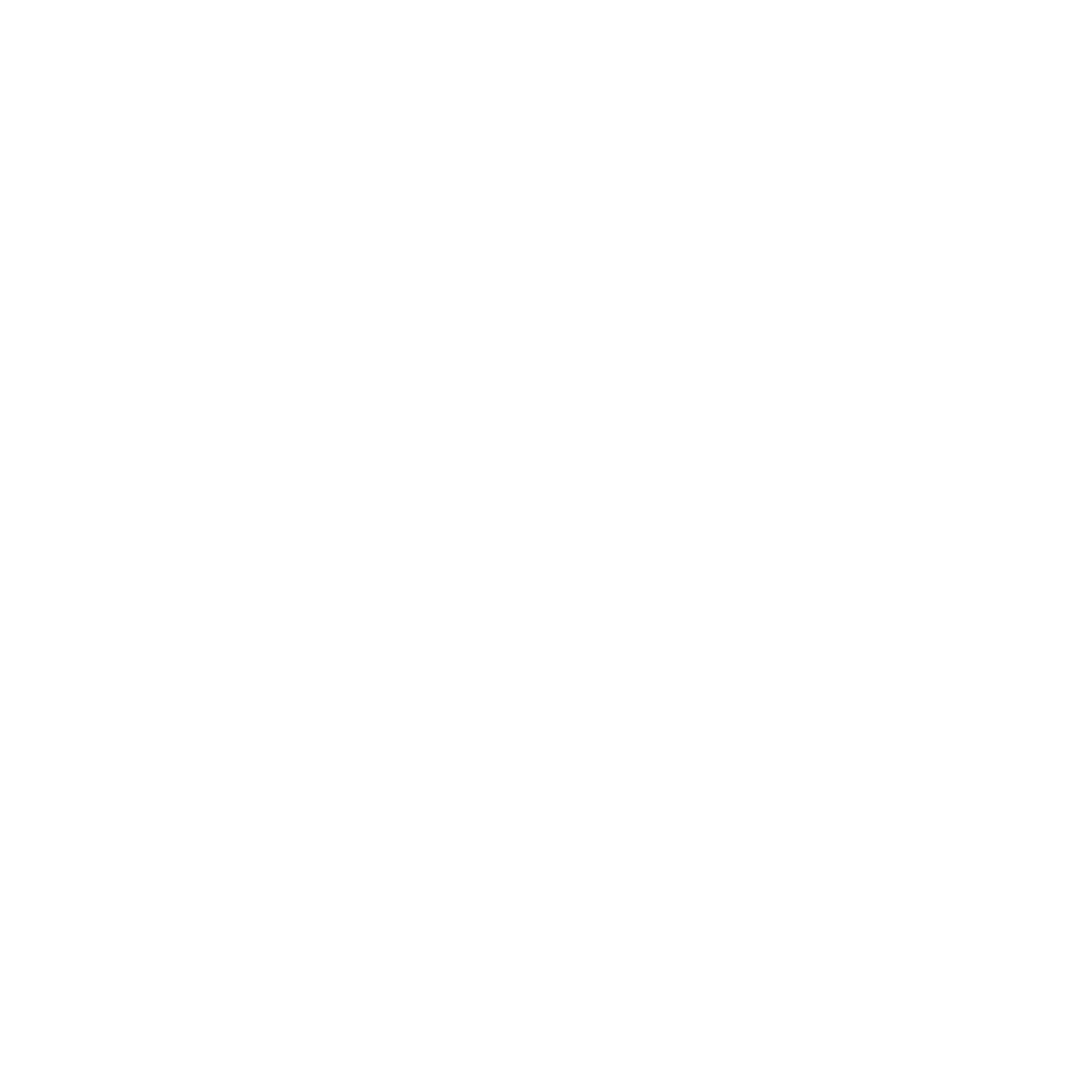SHORT COLUMN
ショートコラム
甘夏のはじまり 第2章_再会
甘夏のはじまり
この夏、ウェブエイトのメンバーが交代で綴るショートストーリーをはじめます。
台本やルールはありません。
登場人物も、物語りの舞台も、自由自在。
このあと、どう展開するかも、その人次第です。
決まっているのは、「甘夏のはじまり」というタイトルのみ。
さて第二章は、夏美のその後が描かれたようですね。

■
3年前のあの日、あの人と出会ったことを思い出しているうちに、
15分も時間が過ぎてしまっていることに気づいた夏美は急いでPCに目を戻す。
明後日は今年一番になるであろう大事なプレゼンがあり、
そのための準備をしなくちゃいけない。
あいにく今日の体の調子はすこぶる良く、頭が冴えている。
この感じであれば今日中には必ず準備は終わらせられる自信があった。
あんなことが起きなければ。
■
最近運動にハマっている夏美は、
ここから車で30分くらいの空港の周りをよく走っている。
お気に入りのブランドのウェアを着て、紫外線対策も抜かりない。
一般的に見てやや細いか普通程度の体型のため、
痩せたいという思いはそこまではないが、ストレス解消と健康維持のためだ。

そのおかげで体の調子が良い日が続いているのは間違いない。代謝も良くなっている。
そんなことを頭の片隅で考えながらひとまずメールのチェックをし始めた。
いつか見たビジネス書でメールのチェックを朝一にするよりも、
その日のうちでいちばん重要な仕事を真っ先に片付ける方が効率的だと書いてあった。
だが、そんなことは関係ない。これが私のモーニングルーティーンなのだ。
溜まっていたメールを返信し終えたところで一息つきながらコーヒーを飲む。
二口目が喉を通り切った時、聞き覚えのある声が背後で小さく聞こえた。
「甘夏さん?」
ゆっくりとカップを置いて後ろを振り返る。
5秒くらいの沈黙があった後、頭の中でやっと繋がった。
3年前のモーニングチケットの人。
私がずっと会いたいと思っていて会えなかったあの人。
あれから何度も何度もあの日が火曜日じゃなかったら、
次の日が水曜日じゃなかったらとどれだけ考えたか。
会う人会う人全員にその時のことを話していた。
まるで恋する中学生のように。
でも、どこに住んでいるのか、結婚をしているのか、
何の仕事をしているのか、何も知らなかった。
分かっていたのは県外から旅行で来ていてドミトリーに宿泊している、
仕立ての良さそうな生成りのシャツを着た女性ということだけだった。
あのとき途中から私が自分のことを一方的に話してしまったからだ。
もしかしたら彼女には不思議な力があって話をさせられてしまっていたのかもしれない。
もう一度彼女の方に目を向ける。確かに目の前にいるのはあの時の女性のはずだ。
声や目は鮮明に覚えているから間違えるはずがない。
そして「甘夏」という響きも。
それでもなにかが腑に落ちていない、
数秒の沈黙を生んだモヤモヤした感じが夏美にはあった。
いや、ザワザワの方が近いのかもしれない。
「どうしたの?甘夏さん?」
「あ、いえ!お久しぶりです。」
どうやら少しぼうっとしていたのかもしれない。
急な返事でいつもより少し声が上ずってしまった。
「ここにいると思ったわ。」
「そうですね。わたし場所でも物でも一度気にいるとかなり執着してしまうタイプみたいで。」
顔が引きつっていないか十分に気をつけながら当たり障りのない返事をする。
その間、このザワザワする気持ちの正体を必死に整理していた。
一つ目は彼女の声だ。
3年前に初めて会った時は、
声はさほど大きくはないがよく聞こえる透き通った声で、
どこか凛とした雰囲気を醸し出していた。
そして、落ち着きの中にどこか芯をつくような、
全てを見透かされているかの口調も特徴的だった。
それが、今はかろうじてその面影があるくらい。
声の大きさは変わっていないのかもしれないがハリが全くなく、頑張らないと聞き取れない。
気を抜いたら「えっ」と瞬発的に言ってしまいそうだ。
なんというか、全体的に暗いというか地味というか。強いていうなら、全く覇気がない。
「甘夏さんはお元気でした?」
「はい、ちょっと仕事が忙しいくらいで毎日元気にやってます。」
「そう、それならよかった。」
「ええと、そういえば、、」
「私はりょう。立花涼って言います。男みたいな名前でしょ。」
「いえ!素敵な名前だと思います。」
私の戸惑いなんかお構いなしに会話が進む。
そして、初めて彼女の名前を知った。あの時のイメージとはぴったりの名前だった。
あの時の彼女には。
しかし、今目の前にいるのは果たして私がずっと会いたかった人なのだろうか。頭が混乱してきた。
声や話し方は百歩譲ってそうだったとしても、外見があまりにも違いすぎている。
おそらく違和感を感じている1番の理由だろう。
3年前は旅行をしていると言いながらも清潔感を絵に描いたような印象があった。
生成りのシャツを着ておまけにどこのブランドかは分からないが、爽やかな香水の匂いがした。
今夏美の目に写っている”りょう”と名乗るその女性は、
薄汚れたTシャツに臙脂色のスカートを履いていて清潔感とは程遠い。逆の意味で目立ってしまう。
クーラーのせいもあるかもしれないが薄気味悪さを感じていた。
長く伸びた黒髪も全く手入れがされていないようだった。
「となり、座ってもいいかしら。」
「ええ。」
「わたし、ずっとなつみさんを探していたの。
あれから一度だって忘れたことは無いわ。一度たりとも。」
そう言いながら彼女は私の隣にゆっくりと腰を下ろした。
名乗った覚えのない私の名前を口にしながら。
|
松本空港
|