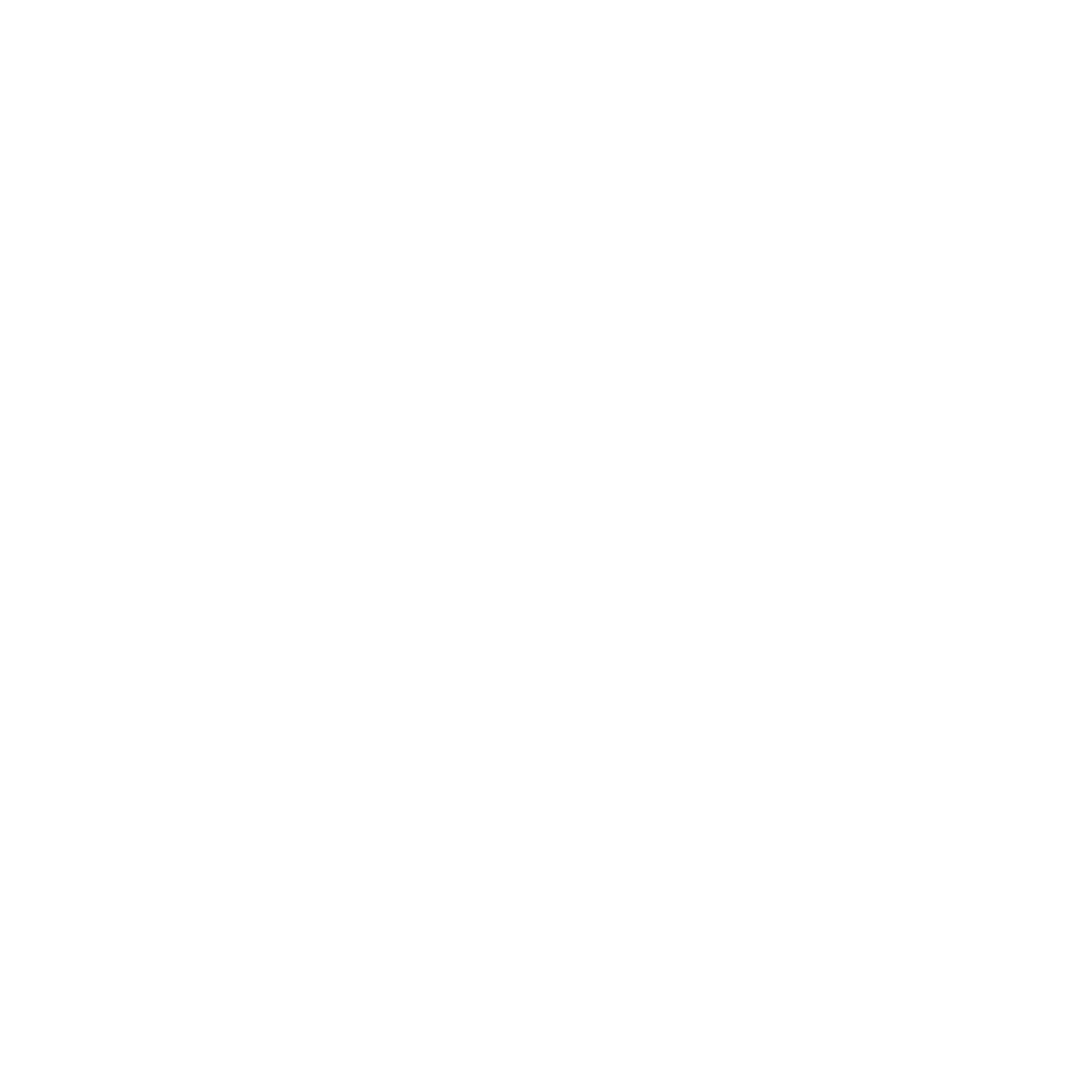TOPICS
トピックス
ショート動画の基本の「き」を学ぶことで、一緒にスタートラインに立つ伴走者でありたい。
こんにちは、ウェブエイトの孫の手(になりたい)石田ゆずまです。
今週は、長野から石川県白山市の商工会議所が主催する「SNS活用セミナー」に講師として伺いました。片道300kmという離れた地でしたが、白山商工会議所の受講者の皆さんはとても温かく迎えてくださり、おかげさまで会場は活気のあるセミナーとなりました。
今回のセミナーを通して、参加された皆さんの課題感には、共通して大きく3つのポイントがあると感じました。
1:「ショート動画の名前は知っているけど、やり方などの手取り足取りがわからない」
ショート動画という言葉は広がっていますが、「実際にどう始めればよいのか」「どんな流れで動画を作るのか」が分からず、最初の一歩でつまずく方が多くいらっしゃいます。撮影アングルや画角、音源選び、テロップの付け方など、検索すればたくさん情報が出てきますが、初心者が本当に知りたいのは“手順”と“コツ”です。
アプリのどこを押せば何が起こるのか、どの設定がどんな効果につながるのかなど、基本操作を目の前で「こうすると良いですよ」と教わるだけでハードルは大きく下がります。情報が多すぎて迷いやすい今だからこそ、初歩から丁寧に学べる機会が大切なのだと強く感じました。まずは30秒の動画をつくってみる体験さえできれば、誰でも発信の楽しさを感じられるようになります。
2:「なんとかやっているけど、『これでいいのか』を相談できる人がいない」
ショート動画を独学でつくっていると、「編集の雰囲気はこれで良いのだろうか」「他の人はどう作っているのだろう」と、不安が重なりやすいものです。再生数や反応が伸びないと、その原因が撮影の問題なのか構図なのか、方向性なのか、自分では判断しにくくなります。
相談相手がいないまま悩みが積もると、動画づくり自体が負担になってしまうこともあります。逆に、ほんの少しのアドバイス――「明るさを上げると見やすくなります」「冒頭の3秒を工夫すると離脱率が下がります」など、具体的な指摘があるだけで動画は大きく変わります。「これでいいのか」を安心して相談できる相手の存在は、発信を続ける力につながるのだと改めて感じました。
3:「同じ会場内で、得意不得意として教え合う文化がない」
同じ会場にいても、「迷惑になったらどうしよう」「聞いていいのかな」という思いが作用し、得意な人と初心者が自然に助け合う文化が生まれにくいことがあります。技術レベルの差があるほど交流が少なくなり、せっかく集まっているのに、皆さんが黙々と作業する場になってしまうことも少なくありません。
しかし、講師と受講者という関係を超えて、会場全体が“学び合う場”に変わると、一気に空気があたたかくなります。動画が得意な人は編集のコツを教え、文章が得意な人はキャプションを手伝い、アイデアが得意な人は企画をサポートする。そんな循環が生まれると、初心者の方は安心して質問でき、経験者の方も自分のスキルをさらに言語化することができます。
一緒にスタートラインに立つ伴走者でありたい
今回のセミナーでは、ショート動画の「基本のき」を共有することで、多くの方と一緒にスタートラインに立つことができたと感じています。しかし、中には「やってみたいけど、やっぱりまだ不安」という方がいることも分かりました。
そんな皆さんのために、私はこれからも“一緒にスタートラインに立つ伴走者”でありたいと思います。ショート動画のはじめの一歩は、誰でも踏み出せます。一人で悩むのではなく、伴走しながら進める環境をこれからもつくっていきたいです。